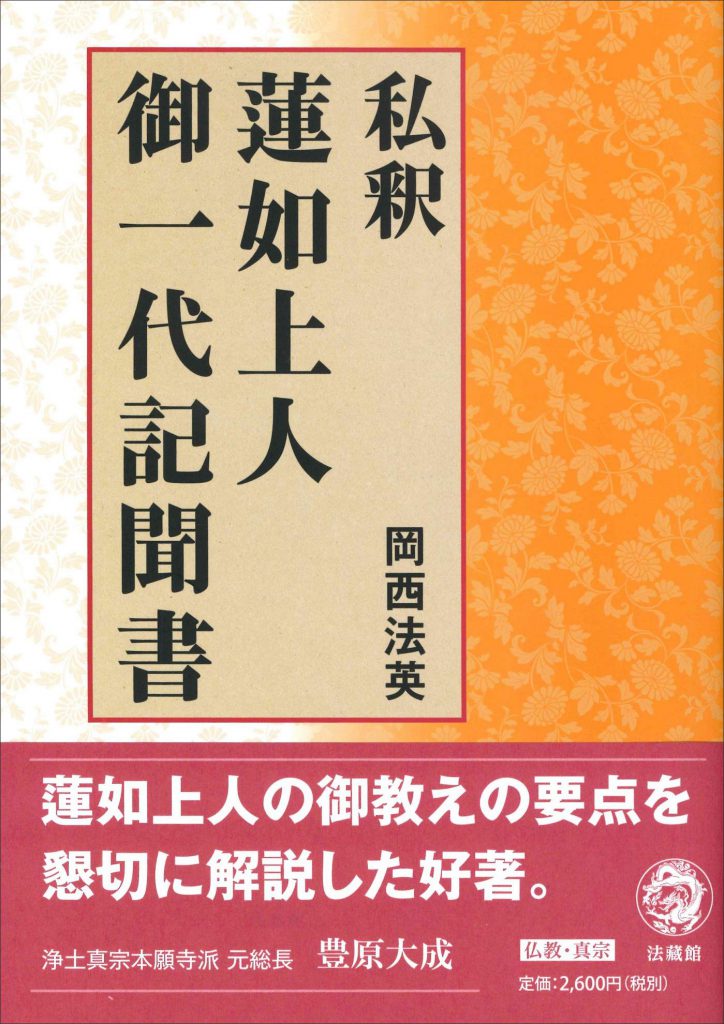イ 悲しみの中のいのち
このやり場のない悲しみが私一人のものでなく、あの人の、またこの人の、そして数知れぬ先人たちの背負ってきたものであったと知らされたとき、幾千億の人々が流してきた涙が、今日は我がまなこから流れ落ちているのだと気づいたとき、大いなる大悲の中に抱かれて涙されている我が身を感じたのです。
私の嘆きはやまないままで癒され転じて、私が受け継いだのは生命だけではなかったという驚きと畏敬となりました。
ロ 受け入れがたい突然死
人の死もさまざまですが、遺族にとっては受け入れに違いがあるようです。年老いて、何かの病で死ぬというのはいわゆる自然死です。交通事故・脳卒中・自殺などは、遺族にとっては突然死です。また、戦争・過労・薬害・公害による死は社会死と呼ばれます。愛する人を突然死で失った方々は、ショックが強く、その死を受け入れるのに時間がかかります。そばにいる人達の支えが必要です。
また、社会死には消えぬ怒りと恨みが残ります。多くの人達の理解と共感で痛みをやわらげなければなりません。
ハ 死んでも父はわが父
「亡き父も草葉の陰で喜んでおることと思います」「亡き父が見ましたらさぞ喜ぶことと思います」こんな言い方をよく聞きます。
しかし、「息子として心から感謝致します」「父に代わってわたくしが見せていただきました。ありがとうございます」と言うほうが無理のない正直な言い方ではないでしょうか。
私の目の奥から、私の耳の底から、亡き父が見ている、聞いているという気がすることがあります。たとえ死んでも父はわが父、だからでしょうか。
ニ 子を失う悲哀
美しく晴れた春の空を見ると、娘の死の悲しみが胸によみがえります。これは美味いと思うとき、死んだ娘を想います。幸せそうな若い女性を見るたびに娘の面影を探します。 悲哀の感情ほど不思議なものはない。子供の死を悲しむ親たちは、その悲哀を失うまいとしているようにさえ見える。そう書いたのは、幾人もの子を亡くした哲学者西田幾太郎でした。
忘れたくない悲しみ。それどころか悲しむことだけが、消えることのない愛別離苦の癒しであるということがあるようです。
ホ 別れの悲しみの中から
思えば 人間界に生を受けて、いのちの不思議を知り得たことほど大きな幸せはありません。
しかし、自我にとらわれ 欲望にしばられる私たちは限りあるいのちを生きる身であることを忘れ、何が真にいのちの輝きであるのか、問うことも稀です。
別れの悲しみの中から、人と生まれ、人と育てられたことの重さを見いだし、いのちあるすべてのものに光あるようにと努め励んで悔いのない道を歩みたいものです。
ヘ 悲しみに寄り添う大悲
葬儀は悲しみの別れというがいつわりのない凡夫の情でありましょう。
そのままを受け入れ、浄土での再開の約束の儀式と転じて下さるのは阿弥陀如来の大悲です。たとえ、遺族が今は無信心であっても、信心の人の姿にならうことが儀式の意義でしょう。
また、被葬者である故人が、無信心であったとしても、遺族が安心してまかせうる阿弥陀如来のましますことを頼もしく仰ぐところに儀式の精神があります。
ト 見られているわたし
逝ける人を想うことは、特別なことではありません。そこでは必ずしも宗教的な受けとめ方は必要と感じられないかも知れません。自分のものさしで考えるのですから。
しかし、逝ける人から見れば今の自分はどうなのかという問いに突き当たったとき、自分のものさしをこえた、何者かの眼差しを意識しないではいられないのではないでしょうか。そこに宗教の世界があるのだと思います。
チ 死は異常事態ではない
遺体の周辺の屏風を逆さにしたり、遺体に衣装を逆さにしてかけたり、枕元にご飯を供えて一本だけの箸を立てたりなど、通常とは反対のことをする習慣が一部に伝わっています。
背景には、死を特別なこと異常なことと見なして日常生活から隔離し排除しようとする発想があります。
しかし、そこで読まれるお経は生を見つめ、死を見つめ通した中から生まれた仏陀の智慧のお言葉なのです。生をも死をも抱きとる真実が説かれています。
リ 衷心にあるものは宗教
何故葬儀に宗教がかかわるのでしょうか。葬儀は、生きることの意味が根源的に問われる場面であり、もともと、死をどう受けとめるかということを通して生きることの意味を明らかにしようとするところに宗教があるからです。
この点から考えますと、よく葬儀の際に用いられる「衷心より(心の底から)」という言葉はそのまま、宗教性の別名であるといえます。その人の心の底にある最後の拠り所こそその人の宗教であるからです。
ヌ 終のよりどころとしての宗教
葬儀は、故人の生涯をとぶらい、自分との縁の重さに思いを致す儀式です。だからこそ、自分の人生において最も大切なもの、より所とするもの、すなわち宗教に従って送るというのは自然のことです。
また、別れの悲しみを癒すもの、生と死を越えて通じ合う道を示すものとしての宗教儀式が行われるという意味もありましょう。
まことに仏法こそ、人間の悩みの中から現れ出た光であり、心の闇路に届く、慈悲の呼び声でありました。
ル 死後までわがまま
素直に生きることの苦手なわがままな私です。だからこそ「死んだあとのことは皆様にお任せします」と言いたいものです。
死後の葬式についてまで自分の意志で采配しょうというのは行き過ぎではないでしょうか。葬式のことは遺族や知人たちにゆだねるべきではないでしょうか。
「死ねば無だ」というなら、「無」が葬式をせよとかするなとか指図するのも変なことです。そもそも、死後にまで人を自分の意志で動かそうとするのはおかしいですね。
ヲ 悼むものの権利
「葬式はしてくれるな」と遺言する人があります。葬式は死んだ人のためという考え方なのでしょう。しかし、後に残った遺族・友人・知人のためにこそあるのだとしたらどうでしょうか。
「皆様方とのご縁の中で生きた故人です。ありがとうございました」は遺族の思い。「故人には良きご縁を頂きました。ご遺族にお悔やみと御礼を申し上げたい」は会葬者の思い。その思いを持ち寄って、命の重さを確かめ合う集いだと思うのです。
ワ 悼むものの誠実
故人が仏教徒でも、喪主・遺族がキリスト教徒であるなら、キリスト教式の葬儀が行われることを非難はできないと思います。
その喪主・遺族にとって衷心からの誠実な追悼は自らの信ずるキリスト教を抜きにした或いはキリスト教の精神に反する儀式によってはできないからです。喪主・遺族には自らの信教に基づいて葬儀を営む権利がなくてはならないはずです。
葬儀は遺族のものであって、故人のものではないのですね。
カ 人のための宗教
葬儀も法要も、ただ死者のみではなく、死者も生者も引き受けて下さってある阿弥陀如来を中心とした儀式であることは幾重にも再確認すべきことです。
しかし同時にまた、信仰を異にする人々とも共に故人を追慕する場であるということになりますから、その点の配慮が必要になります。宗教的押し付けや、侮蔑にならないことが大切でしょう。
宗教は人のためにあるのであって、宗教のために人がいるのではないのです。
ヨ 喜怒哀楽はバランス棒
うれしいときは笑い、くやしいときは怒り、悲しいときは泣けばよい、それが人間だと言います。
綱渡りをするのに長い棒を持ってバランスをとるように、現実と自分との間の、感情という摩擦音を手がかりにして、私たちは、自分の居場所をさぐり当て、現実に向かい合おうとしているのかもしれません。
感情に流されず感情を失わず。感情をバランス棒にして、欲得と愛憎うずまく人の世に老病死・愛別離苦のいのちを生きる。すごい神通力ですね。たいていは誰もがそれなりにやっていることですが。
タ 断末魔
断末魔の苦しみという言葉があります。これが死に対する恐れに付随して、人によっては死そのもの以上に恐れられているようです。しかし、現代の脳医学はそんなものは存在しないことを教えてくれました。断末魔の苦しみというのは、そばで見ている人が想像したものだったようです。
自分はまだ当分死なないはずだと思っているからこそ、他の人の死を前にして抱く、死に対する恐れから生まれた観念なのかもしれません。
レ なすべきをなし終えて
親鸞聖人は、その弟子明法房の死を知ったとき、「ご往生、めでたく候」と手紙を遺子に当てて出されました。明法房は、もと弁円という名の山伏で、親鸞聖人を殺そうとしたこともあった人です。
「お前は今こそなすべきことをなし終えたのである」という、一子ラーフラ尊者が悟りを得た日に釈尊が言われた言葉を思い起こします。
なすべきことをなし終えることとしての死、めでたき死でありたいものですね。もちろん、自らは寂しく、残る者には悲しいに違いありませんが。葬儀は人生完成記念式典でもあるはずです。
ソ 川の流れとは違って
「川の流れのように」という美空ひばりの歌の文句を聞いて思いました。「人生は川の流れのように」は帰する所があってこそ安らぎであるはずだと。そしてまた、人生は川のように上から下へと流れるのみではないのではないかと。過去はやりなおせないが、過去を見直し、受けとめなおすことで、これまでのままなら決まっていたはずの将来も変わってくる。流れを変えることができるのが人生だと。川には意志も努力もないが、人間には意志があり、努力があるではないかと。
ツ 親心の力
「母に何かをしてもらおうなどと当てにする気持ちなどなかった。ただ、あれもこれもしてあげたいと思っていただけ。ところが、死なれてみると、何か胸の底に穴があいて力が抜けたよう。今までどれだけ母親の存在を力にしていたかを思い知らされた」と述懐した方がありました。
母が見ている、心配している。悲しませてはならない、喜ばせたい。そんな思いが、この方の生きる力の下支えだったのですね。
「如来様の力だ、他力だというのは、そんな親心の力みたいなものだったんですね」この方はそうも言われました。
ネ 遺族への励まし
父の葬儀に参列してくださった予想外の方々に対して、ほんとうにうれしくあり難く思ったものです。失った父の存在の大きさを知らされたと同時に、父もわたくしもいかに多くの人達の愛情と支えの中で生きていたかを思い知らされたことでした。
お参りにはみえなかった膨大な数の方々一人ひとりの恩情に思いをいたさずにおれませんでした。父の後を生きるわたくしに、大きな励ましと力づけを与えた葬儀であったと思い起こします。
ナ 死を悼む姿の尊厳
人の死を悼み、悲しむ姿にこそ人間の尊厳を強く感じます。
驚いたのはテレビのドキュメンタリー番組で見た象のすがたです。いわゆる象の墓場を通りかかった象の一群の様子は、それまでとは明らかに異なった厳粛さで哀愁の感情を示します。中の一頭はある遺骨に対し、それが肉親のものと知ってか、立ち止まって愁嘆のしぐさを表します。ああ、象にもわかるのかと感慨を抱きました。いのちの尊厳を垣間見た思いです。
全ての生き物を「有情」と呼んできた仏教の伝統の意味する所をあらためて考えさせられたことです
ラ 死は時代とともに
死をどう受け止めるかは、時代とともに変わってきたということを明らかにした『死と歴史』の著者フィリップアリエスは、野蛮なる死・儀式の中の死・自己の死・愛するものの死という区分を立てて人の意識の変遷をたどりました。
現代は「野蛮なる死」の時代に逆戻りしている。死を、思いがけない災い・不当なる不幸・どう対応してよいかわからない恐怖の的と感ずる人が多くなったといいます。そして、神への信仰が薄らぐのに比例してお墓への愛着が強くなったと指摘しています。考えさせられますね。
ム 私の死・あなたの死
死といっても、万人共通のものという観念上の死、他人の死と、愛するものの死、おのれの死とでは、自分にとって意味が大きく違うのではないでしょうか。
その人の信仰のありようによっても死に対する受け止め方は大きく変わるものです。死に対する受け止め方の違いはそのまま生きることの意味をどう考えるかに反映されます。 『死と歴史』の著者フィリップアリエスは、後年、大病を患う夫人を自宅療養させ、時間の大半をつぎ込んで看護につとめたといいます。それが、死の研究を通して学びとった生き方だったのでしょう。
ウ 病院での死
最近はほとんどの人が病院で死を迎えるようになりました。病院は生きるために治療を施す所というのが今までの常識でした。しかし、緩慢で苦痛少ない死を迎えるための場所という役割も期待されるようになってきているようです。
このことは、死を間近に控えた人の「見取り」が、家族の手から病院の職員にゆだねられることを意味します。家族のサラリーマン化がもたらしたものです。子育てが保母さんにゆだねられているのと同じ理由です。
寂しい気がしますが、この状況を変えるのは個人的な努力では困難です。あらゆる立場の人々の共感と連帯、そして企業の協力、政府の支援が必要でしょう。
ゐ 死んで生き返った人
一度死んで生き返った、あの世を見てきたという人が時々います。その時の心理的体験は洋の東西や時代をこえて共通点が多いようです。
実は、本当に一度死んだわけではなく、意識の深い部分までが停止した状態から意識が回復してくるときの心理状態には共通のパターンがあるということなのでしょう。自分が死んだと思うのは生きている証拠なのですから。
それにしても、その時にいわゆる断末魔の苦しみというものを経験した人はいないわけですから、いらざる恐れを抱かなくてもよいという証言だともいえます。
ノ 死後の世界
死後の世界ということが言われます。自分が死後にゆく世界という意味に使われるのがふつうです。しかし、自分が死んでいなくなったあとのこの世界という意味に取ることもできます。
何処へも行き場所を持たないで、ただ朽ち果てるというのも寂しいことですが自分が死んだ後のことなど知るものか、死んだらしまいだというのも悲しいことです。
自分か死んだ後に生きる者達とも心通うような道を歩きたい、後に生きる者達のために何かできることがあるのではなかろうかというのが自然な考え方ではないでしょうか。
オ 死後に残すもの
自分が死んだ後の人達のためにと、大きな努力をはらって良き遺産を残して下さった数知れぬ先人たちがあることを忘れていました。
その遺産をただ利用するのでは申し訳ない気がします。私たちにかけて下さった願いをくみ取り、その志を受け継いでいきたいものです。どう生きるかも大切ですが、何を願って生きるか、誰のために生きるのかも忘れてはならない大切なことでした。
自分のためだけに生きているのなら、死んだらそれでしまいでしょうが、死んでもしまいにならない願いがあってこそ、いのちは光かがやくのではないでしょうか。
ク 故人を偲ぶ
ままならないのが人生だといいます。一人一人与えられたものがみんな違う中で、望まないまま投げ出されたその人なりの現実の中で生きるのです。世間がままならない以前に自分自身がままならない。わかっちゃいるけどやめられない。自分で自分に愛想が尽きても、生きなくてはならない。自分一人の身ではないのですから。
そう考えたら、今までその人に対してどんな思いを持っていたとしても、今日からは、「ようこそ。ご苦労さまでした。ありがとうございました」と受けとめなおしたいものです。
ヤ 遺影
葬儀の際に飾られる遺影は、大抵の場合、近年中の写真が多いのですが、長い病気の末に亡くなった場合や、余りに高齢の場合には、かなりさかのぼった時のものを掲げることもあります。教科書などに出てくる歴史上の人物などは活躍期のものが多いようです。
実際、縁遠い人のイメージほど元気だった時のものが多いことに気づきます。最晩年の顔とイメージは親しい人たちだけのものかも知れません。それにしても、親鸞聖人の御影はずば抜けて老いていらっしゃることです。
マ 故人の口癖
亡くなった後で思い出される言葉にもいろいろありましょうが、その人の口癖を思い起こすことが多いのではないでしょうか。口癖はその人の人柄や生きかたと一体になったものですから、その人の声色や表情までも一緒に浮かんできます。
ひるがえって、自分の口癖とは何だろうかと考えてみますと、どうも意味のある口癖などは持っていないことに気づきます。家族や友人に言わせれば、きっと何か口癖があるのでしょうが、あまり値打ちがある口癖ではなさそうです。生きかたが生半可だからでしょう。恥ずかしいことです。
ケ 世間虚仮
死後にその人の口癖が伝えられた最初の例は、聖徳太子の「世間は虚仮なり。唯、仏のみ是れ真なり」という言葉だと聞いています。仏法を、人の世のありのままを照らしだす鏡と仰いで生きられた聖徳太子の風貌を伝える言葉です。
家永三郎氏は、この聖徳太子の言葉をただ一つの励ましの力として、あの長い教科書裁判を戦ったのだと語ったといいます。先人が生涯をかけてつむぎ残した言葉が、後の世に生きる者の光となり、力となった例です。
フ 遺産
近頃は遺言状といえば、財産分与というイメージが強くなってきているようです。家族に財産以外のことについて遺言状を残す人は案外めずらしいのかもしれません。
しかし、遺産ととは何かと考えると、お金や家屋敷や土地は、ほんの一部で、実はその人の生き方、心に残る言葉、注いで下さった温情の記憶、身につけさせて下さった行儀作法や技術、文化など、形のないもの、言葉で表せないものが多いのではないでしょうか。自分がうけついだ心の財産表を作ってみるのも意味のあることかもしれません。
コ 無形の家宝
子孫に美田をのこさずという古語があります。きっと安穏に暮らせるような財産を受け継いだわけではなく、自らの力で人生を切り開いた人の言葉であろうと思います。
そして自ら人生を切り開く力こそ、親先祖から受け継いだ宝だから、これを子孫にも受け継いでもらいたいという心なのでしょう。片方には、親の財産を食いつぶすという嫌な言葉があります。
形あるものは本当の遺産ではない、心を受け継ぎ、生き方から学べという戒めでしょうか。
エ 墓前の花
「死んで花実が咲くものか」といいます。生きていてこその悲しみ苦しみであり、喜び楽しみではないか、前向きにいこうという意味でしょう。必ずしも死んだら終いだということではないと思います。
実際、本人は不遇の人生をおくったけれども、後世に大きな遺産を残し、人々の心の中に生きつづけているという例は数えきれないほどあるのではないでしょうか。十字架のイエスはその典型かも知れません。
しかし、それも一面ではその志を受け継いだ後人の力であったはずで、先人の後を生きるわたしが問われるのでしょう。
テ 北枕の由来
釈尊をはじめ初期仏教の修行者たちは、野宿暮らしの遊行生活を送っていました。寝るときは、頭を北に、顔は西に右脇を下に寝る習わしでした。釈尊がお亡くなりなるときもその形でした。後世、舎屋の中に住むようになった仏教徒たちもこれに倣って臨終を迎えるようになったのです。
釈尊を真の導き手と仰ぐ仏教徒の習わしなのです。ですから部屋の向きを無視してまで北枕にこだわることはありません。
ア 通夜のこころ
通夜は故人とのなごりを惜しむためのものであることはもちろんですが、別れの悲しみを通して、いのちの重さを思い、如来の悲願を仰ぐところに大切な点があります。そこに通夜勤行の意味もあるのです。
眠ったら亡者に連れていかれると恐れて眠らないというのでは、余りに悲しい考え方です。灯明・線香を絶やしてはならないとこだわる必要はありません。死者のためではなく如来を敬うためのしつらえなのです
サ 仏弟子になる儀式
まだ、帰敬式(おかみそり)を受けていない方の場合は、出棺勤行の前に導師の僧侶によって帰敬式が行われ法名がつけられます。
元来、帰敬式は仏法僧の三宝に帰依し、仏弟子として生きる決意を固めるための儀式で生前に受けるのが基本です。生前にその機会がなかった場合に導師の僧侶が代行するのです。仏弟子として送り出すという趣旨です。法名といえば、死を連想するのは的外れです。
キ とむらいの儀式
仏式の葬儀は、出棺勤行と葬場勤行をかたどったもので、いわゆる故人に別れを告げる告別式ではありません。
弔電や弔辞も故人へのものではなく、遺族へのとむらいとねぎらいの形をとるのが本当です。死という現実を直視しようという仏教の基本精神に立っているからです。
死者を浄土へ送る呪術ではありません。人間には自分で浄土へ往く力も、ましてや、ひとを浄土へ送る力もないからです。
ユ 主役は喪主・遺族
死者ではなく、喪主・遺族に対して、とむらいを述べるのが弔電・弔辞です。「弔い」と「お悔やみ」の語義に立ち返って考えればよくわかるはずです。
また、弔電の発信者の名前を長々と読み上げる例を目にしますが、会葬者が欠席者の名前を拝聴するというのは矛盾したことではないでしょうか。
特に政治家の名前が読み上げられるとき、葬儀の政治利用という不敬に当たる懸念があります。
メ 執着と恐れを越えて
お骨にはさまざまな恐れとタブーがまつわっているようです。遺骨は故人の存在を偲ぶよすがというべきものでありましょう。粗略に扱うべきではありませんが、度を越した愛着は意味のないことではないでしょうか。
形体あるもの、壊れゆくものへの愛着を越えて不滅の真実に帰すところに、仏法の精神があります。壊れやすい素焼きの土器に遺骨を納め、南無阿弥陀仏を墓標の正面に彫る。見慣れたお墓のすがたはそれを教えています。
ミ 故人を偲ぶ
亡き人を偲ぶとき、私たちはその人の死ではなく、その人の生きたありさまを偲ぶのです。
すでにその人がいなくなってしまったことを、いくら嘆いてみても何も生まれません。その人と共に生きることができた事実を大切にしてゆくほかはありません。
節目ごとに法要をいとなむ際も、あらためてその人が生きた事実をふりかえって、今の自分のいのちとのつながりを確かめ、一歩一歩を生きることの重さに思いを致したいものです。
シ 献杯
近頃、法要の後の食事の際に「献杯の音頭をどうぞ」という言葉をよく耳にします。何かしら違和感があって気持ちよくありません。
法要につきものの食事は、元来「おとき」といって如来様にお供えしたお仏飯を分け合って頂くのが趣旨です。如来の慈悲と故人の労に感謝しつつ「頂く」のです。
「死者に杯を献ずる」というのはこじつけがましく不遜な感じがします。「故人を偲びながらありがたく頂きましょう」と言う方が自然に思えます。
ゑ 法要は三宝供養
法要というのは、字義としては仏法の肝要という意味ですが、儀式としては仏法僧の三宝を供養することを指します。
仏事と称して、如来に供物を供え、お飾りするのは仏の供養です。法事と称して読経するのは、仏陀説法の再現で法の供養です。おときと称して、僧侶と参集者にご馳走するのは僧の供養です。
誰もが目指すべき人格の完成者である仏と、その不滅の教えである法と、その法を共に聞き伝える僧の三つこそ、我のみならず人の世のよりどころであったとの喜びと感謝の表現です。
ヒ 葬式の義理まいり
最近のお葬式は職場関係の参列者が大半のことが多いようです。単なる義理参りだという人もあります。しかし義理参りも、故人の社会的存在としての重さの証明であり、遺族へのいたわりのうちだと思います。
昔の村八分においてすら、火事のときの手助けと、葬儀の際の協力の二分だけは別ということになっていたことを思い起こさせられます。
今の言葉でいえば、この二つは基本的人権であるという思想で村は成り立っていたということでしょうか。人情の暖かさを失わない社会であってほしいものです。
モ 香・灯・華
灯火は闇をはらい安心と自在をもたらします。薫香はなごみと安らぎを、供花はいのちの喜びを表します。仏前に供えられるこれらは、もともと賓客をもてなすためのもので、最大限の尊敬を表します。ことばで表現すれば、ようこそようこそということになりましょうか。
セ 命日
亡くなった日を命日と呼ぶのは何故でしょうか。元来は命過日であったのが略されたのだという説があります。
しかし、命という字には、天命・運命・命令という熟語が示すように、自分の意思とはかかわりなく、与えられたもの、我が意のままにはならないものという意味が含まれていることを考えれば、死去の日はなるほど命日だとも思えます。もっとも、そういう観点からいえば、誕生日こそ命日と呼ぶにふさわしいともいえます。生まれるも死するも天の命であると考えた古代中国人の思想がうかがえます。
![[教願寺]岡西法英の浄土真宗](https://kyoganji.com/wp/wp-content/themes/kyoganji/assets/images/kyoganji-logo.svg)